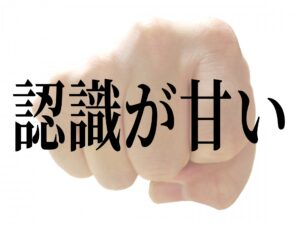親が子どものためを思って、つい口を出してしまう―それ自体は自然なことです。ですが、あれやれ、これやれ、と細かく指示することを繰り返していると、子どもは「言われなければ動けない人間」になってしまいます。
分からないことがあったら、自分の頭で考えようとせず、「どうせ親が教えてくれる」と待つ姿勢になってしまう。質問をすることもありません。判断力は「誰かに言われてから動く」では育ちません。その積み重ねが、試験本番で「これ、どうしたらいいの?」という場面に出くわしたとき、自分で何も決められないという形で表れます。
さらに困ったことに、判断できない子どもの肩を持つ親もいます。「本人の力不足では?」という指摘を受けても、「うちの子は悪くない。言ってくれなかった先生や塾が悪い」と外に責任を求めてしまう。これでは、子どもが自分の非を直視し、立ち上がるチャンスすら奪われます。
今の入試は、かつてのように「知っていれば解ける」形式ばかりではありません。その場で読んで、理解して、判断して、答えを出す―こうした未知への対応力が問われる場面が増えています。ますます、「自分で考える力」がなければ乗り越えられません。
子どもが間違えたり、困ったり、恥をかいたりすることを、親が先回りして防ごうとするのは、ある意味で「過保護」という優しさの暴力です。転ばせてください。自分で立ち上がる機会を与えてください。親が全部やってしまっては、成長の芽を摘んでしまいます。
「失敗させろ、恥をかかせろ」
この覚悟を持って、子どもの自立を支える関わり方を、あらためて考えてみてほしいと思います。