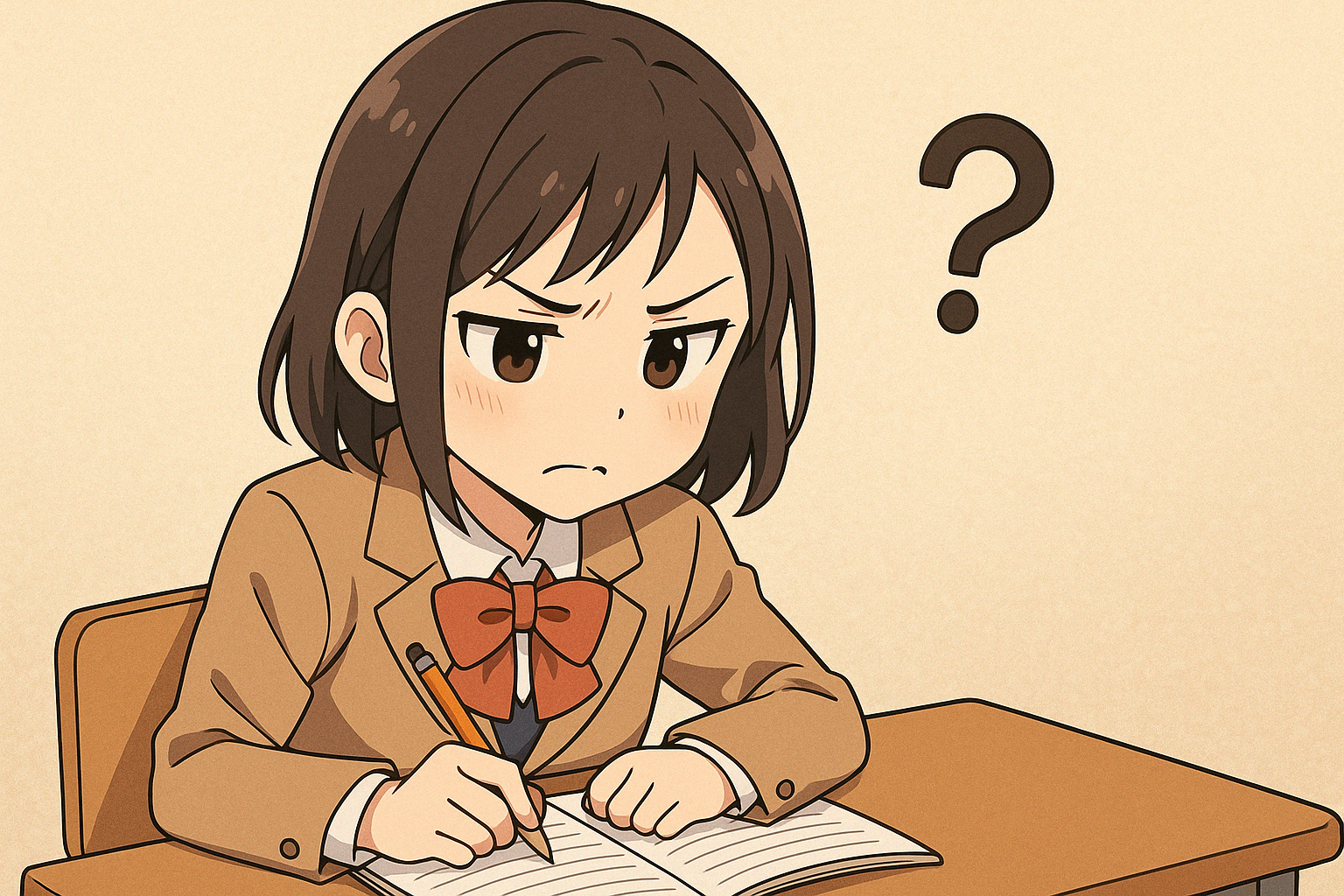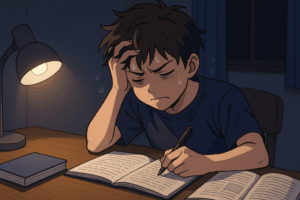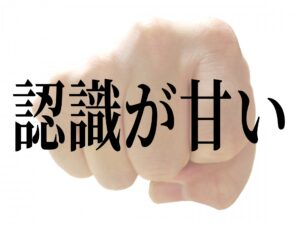前回の話を読んで、こう思った人もいるかもしれない。
「でも、どれくらい勉強すれば“足りる”の?」
「まわりの子って、本当にそんなにやってるの?」
今回は、そんな疑問に答えるべく、“上位層が実際にやっている学習量”を具体的に見ていく。
授業以外の「自学時間」で差がつく
勉強時間というと、「塾に通っているから大丈夫」と思うかもしれない。
けれど、成績を分けるのは授業の中身よりも、その“外”の時間だ。
つまり、自分で問題に向き合い、反復し、覚え、考え抜いた「自学」の時間。
これこそが、受験における真の実力をつくる。
歩実塾でも、自学のための時間は用意している
歩実塾では、中学生に対して
塾内で週7~10時間程度の「自学時間」を確保している。
演習・補習・振り返りなど、目的を持った学習ができる環境だ。
しかし、だからといって、それだけで十分とは言えない。
なぜなら、上位層はそれ以上に、自宅やスキマ時間もフル活用して勉強を積み上げているからだ。
偏差値70の子が、どれだけ“自分で”やっているか
たとえば、ある中3生。
県立トップ校を目指し、偏差値は68~70。
その子が日々積んでいる「自学時間」はこうだ:
- 平日:3時間以上 × 5日 = 15時間超
- 土日:5〜7時間 × 2日 = 10〜14時間
- 週合計:25〜30時間
これには、塾の授業時間は含まれていない。
本人が「自分で勉強した時間」だけだ。
これだけやっていても、「まだ足りない気がする」と語る。
だから、この層は強い。
一方、その下の層はどうか
- 平日:1時間 × 5日 = 5時間
- 土日:合わせて1〜2時間
- 週合計:6〜7時間
その差、1週間で20時間以上。
たった1か月で80時間以上の差になる。
そして夏休み:
- 上位層:1日6〜8時間 × 40日 = 240〜320時間
- 中下位層:1日2時間 × 40日 = 80時間
➡ 夏だけで160時間以上の差がつくことになる。
偏差値は“時間”で積み上がる
「偏差値を5上げるには約200時間の学習が必要」とも言われる。
偏差値55の子が、65を目指すなら、
追加で400時間が必要になる。
それを「夏で挽回」は、現実的に無理。
今から日々の積み重ねが必要だ。
量を積んだ者だけが、質を語れる
- 10問で効率を語るより、まず100問やってみよう
- 勉強法を調べる前に、1冊やりきってみよう
- 「集中できない」と言う前に、2時間ぶっ通しでやってみよう
“疲れるくらい勉強した”経験を持った者だけが、
「どうすればもっと良くできるか」を語れる。
まとめ:自学時間は“最低ライン”にすぎない
歩実塾では、週7~10時間の自学時間を塾内で確保している。
だが、それだけでは十分とは到底言えない。
上位層の勉強量に比べれば、まだスタート地点にすぎない。
ここからどれだけ自宅でも積み上げられるかが、
偏差値の天井を決める。
- 平日:3時間以上
- 土日:5〜7時間×2
- 授業を除く「純粋な自学」で週25〜30時間
「やるしかない」と行動に移した者から、成績は動き出す!