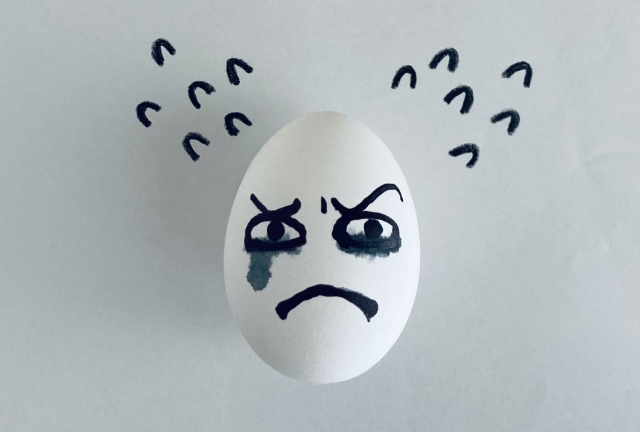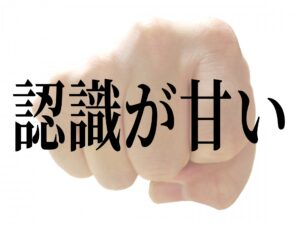■ はじめに
「自分でやれます」──とても頼もしい言葉に聞こえます。
でも、実際に成績が伸び悩んでいる子ほど、この言葉をよく口にします。
なぜでしょうか?今回はその“自力”の正体を、少し掘り下げてみたいと思います。
■ 自立じゃなくて、ただの“ひとりよがり”
「自分でやれます」と言いながら、実際には“自分の世界”に閉じこもっているだけ。
こちらがアドバイスをしようとすると、
「それ、知ってます」
でも結果は? 点数は? 成績は?
──ついてきていない。
知っているつもり、できているつもり。
その「つもり」が、成長の妨げになります。
■ 間違いを直す気がない子は、伸びない
勉強とは、“間違いを修正する”営みです。
しかし、「直されたくない」「言われたくない」という態度では、成長など望めません。
修正を拒む子は、成長も拒んでいるのと同じ。
大人の目線や助言から逃げ続けている限り、変化はありません。
■ 解き直しで「解答ください」と言い出す矛盾
間違えた問題をもう一度考え直してごらん──
そう伝えると、返ってくるのはこの言葉:
「先生、解答もらえますか?」
いや、それじゃ“自力”じゃない。
やっているのは「復習」ではなく、「写経」です。
本当に“自分でやる”というのは、考える責任も自分で引き受けること。
都合のいいところだけ“自力”を名乗らないでほしい。
■ 指導に合わせない=まだ“お子ちゃま”
こちらが方針を示しても、「いや、自分はこのやり方で」と受け入れようとしない。
大人の助言に耳を傾けず、ルールにも従わない。
それって実は──
ただの“反抗期”です。
合わせようとしない=伸びない。
これは、どの年代でもどの教科でも変わらない鉄則です。
■ 本当にできる子は、黙って結果を出す
本物の“自立”は、言葉ではなく行動と結果で証明されます。
「自分でやれます」と言わない子ほど、自分でやっています。
口ではなく、点数で語れるか。
それが、実力の証です。
■ 最後に…そして、困ったら「親に頼る」
「自分でやります!」と元気に宣言した子が、
いざ問題につまずくと──
「お母さんに聞きます」
「パパにやってもらいました」
ちょっと待って?
それ“自力”ではなく、ただの親力です。
「自分でやる」と言って逃げたのに、最後は親に泣きつく。
このパターン、実はとても多いのです。
■ 結論
「自分でやれます」と言うなら、
- 人の話を聞き
- 間違いを認め
- 環境に合わせ
- 解き直しも責任を持ち
- 困ったときは逃げずに向き合う
ここまでできて、ようやく“自立”と言えるのです。
■ おわりに
勉強において大切なのは、「ひとりでやる」ことではありません。
「自分の弱さを認め、必要なときに助けを求める」
その姿勢こそが、真の“自立”へとつながります。
さて、あなたのお子さんは本当に「自分でやれて」いますか?
それとも、“やれているつもり”で止まってはいませんか?