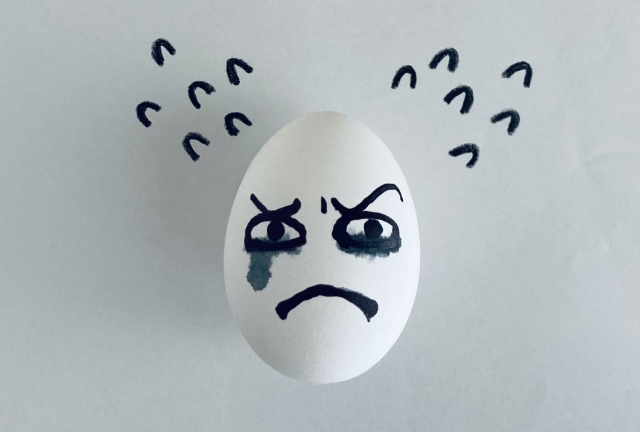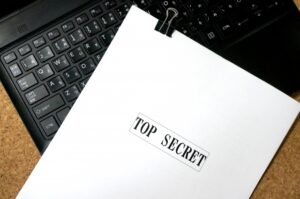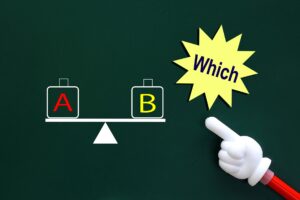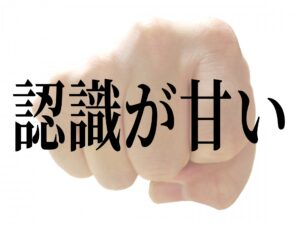ある昔話に、こんな話がある(神奈川県公立入試古文)。
盗人がある僧に「助けてほしい」と祈願を頼んだ。だが一向に効果が現れず、怒ってこう言い放つ。
「お前を頼りに願をかけたのに、何のご利益もなかった。だから今日からは、もうお前のことなど祈ってやらない」
すると僧は、穏やかにこう答える。
「私は頼まれて以来、片時も休まず、あなたのことを祈ってきました」
飢えた僧を井戸に降ろして水を飲ませることになり、盗人は縄で僧を下ろした。
僧が「上げてください」と言ったので引き上げようとしたが、どうにも重い。
よく見れば、僧は井戸の中で大きな石にしがみついている。
盗人は怒って言う。
「そんなものを抱えたままで上げられるはずがない。石を放せ」
僧はそれに応えて言う。
「それと同じです。あなたが“悪い心”を手放さなければ、どれほど私が祈っても、救うことなどできません」
―これは、『伊曾保物語』という、今から約450年前、室町時代の末に日本で書かれた教訓話である。
この話、塾の現場でもまったく同じだと感じる。
塾がどれだけ質の高い教材を用意しても、
講師がどれほど情熱を込めて指導しても、
本人に「学ぶ気」がなければ、何も届かない。
親が塾を選び、塾が環境を整えても、
「変わりたい」という意志が本人になければ、
結果など出るはずもない。
時間とお金が流れるだけだ。
だから歩実塾は、最初にはっきり伝える。
覚悟を持って来い。
その覚悟さえあれば、塾は全力で応える。
「変わりたい」と心から思ったその瞬間から、歩実塾は味方になる。
だが、変わる気のない者に、何を与えても無駄だ。
それが、室町時代の日本人が語り残した、今も通じる真理である。