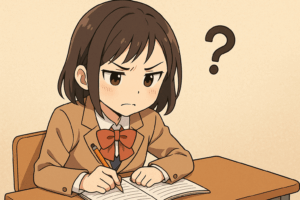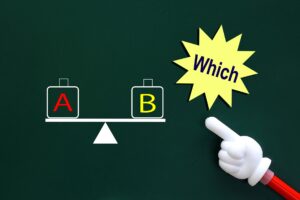歩実塾では、中2はほぼ中学内容の英文法を終えているため、この夏、中3と一緒に某県の公立高校入試問題にチャレンジしてみました。
「公立入試なら基礎重視だから、日頃しっかり取り組んでいる塾生なら楽勝でしょ。満点は何人出るかな?」と期待したのですが―
結果は わずか1名にとどまるという、、、
何が難しかったのか?
なぜ点が伸びなかったのか?
答えは 単語レベルの高さ にありました。
ちょっと前の入試なら注がついていたような単語が、今は「当然知っているでしょ」とばかりに注なしで出てきます。そこで面食らってしまった可能性が高いのです。
たとえば―
affect, influence, thin, develop, thanks to, feature, attach, various, provide, produce, electricity, release, carbon dioxide, environment, improve, flow, challenge, realize
といった語彙。
入試の変化と今後の課題
これらの単語は、難関私立を目指す生徒にとっては「知っていて当然」のレベル。
ところが、公立入試でも普通に出題される時代になったのだと改めて痛感しました。
背景には、ここ数年で一気に難化した 教科書改訂の影響 があります。基礎を大切にすることは大前提ですが、同時に 語彙力の底上げ が不可欠になっているのです。
まとめ
- 公立入試といえど、語彙力が合否を分ける時代。
つまり「文法や構文の基礎ができている」だけでは戦えません。
これからは 語彙で差をつける ことも重要な課題となってきます。
例えば、中2難関SKコースはこの夏、中3の夏期講習のテキストを使って夏を過ごしましたが、その中にあった単語コーナーに収められていた単語は早々に習得しておきたいですね。