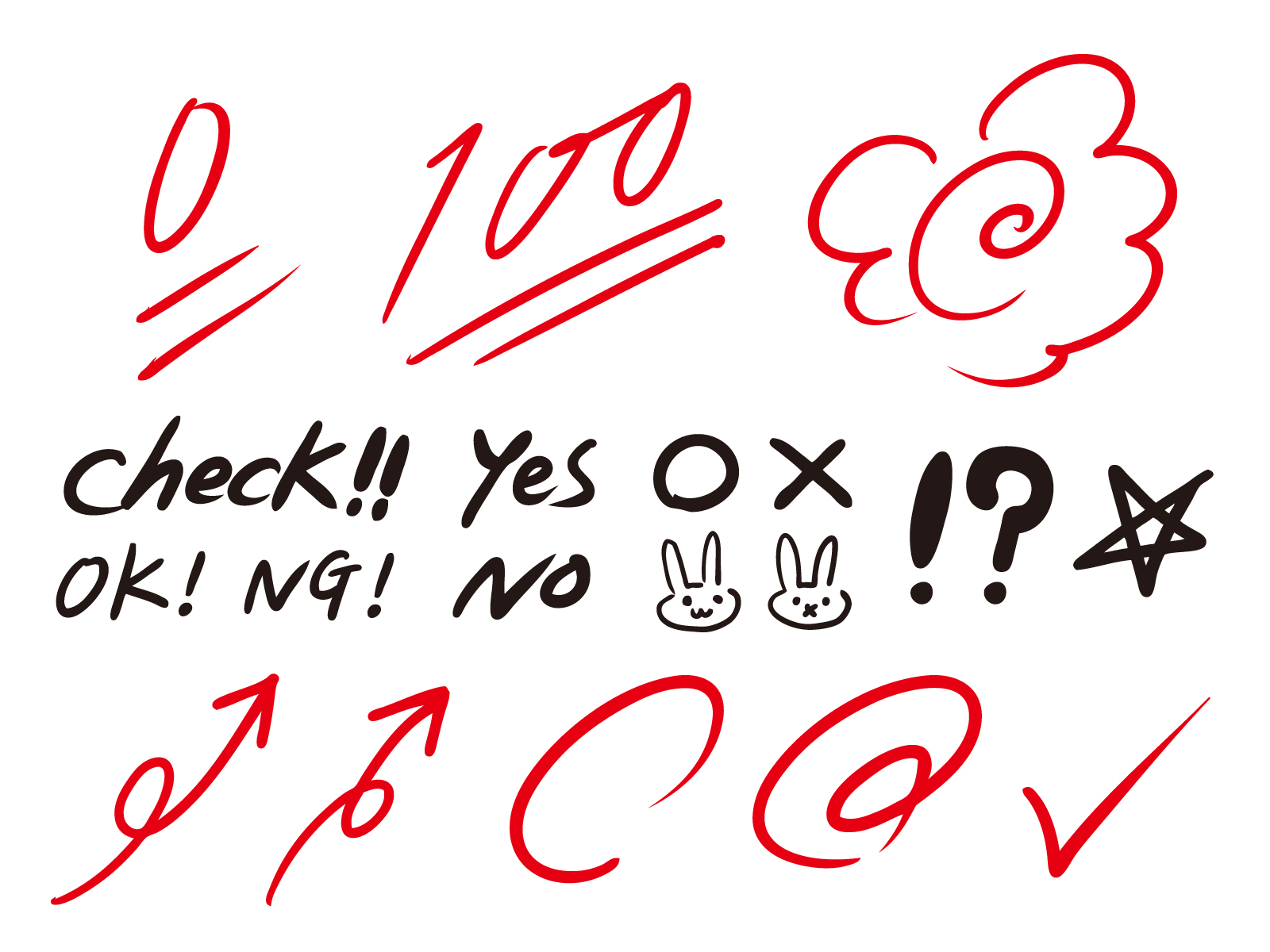中3はふだんの小テストに加えて、週末ごとに大きなテストを実施している。
偏差値を出したり、過去の卒塾生の成績と比べたりすることで、今の自分の位置を数字で突きつけられる。ここで受ける刺激こそが大事だ。
ただし、本当に大事なのはテストを受けた瞬間でも、解説を聞いている時間でもない。返却されてからの「直し」こそが勝負を分ける。
どの教科でも共通して言えるのは、間違えた問題をそのままにしておいては絶対に伸びないということ。
「なぜ間違えたのか」「どう直せば正解できたのか」を掘り下げ、ノートに残し、次の自分の力に変えていく。その作業をサボったら、テストを受けた意味が半分以上なくなってしまう。
科目ごとに復習の仕方は少しずつ違う。英語長文なら音読をひたすら繰り返す。数学なら解き直してできるようになっても、そこに含まれていた重要事項、すなわちポイントをまとめ、次に同じ型が出たとき落とさないようにする。国語なら根拠を言葉で説明できるようにしておく。難解な語句もこういうことだよ、と説明できないといけない。
各教科、直しのやり方は違っても、直しをやらない限り、努力は実を結ばない。
だからこそ、返却後はガリガリと自分の弱点をえぐりにいくくらいの気持ちで復習してほしい。
さて、今日の難関SKの国語で扱った次の文、スラスラもう意味が取れるようになっているだろうか?
生成文法論の、特にピンカーの拠って立つ進化論的な側面から、言語獲得のための遺伝変容が自然淘汰を生き抜かせたとする立場には、生物進化という論理の筋が通っている。言語の種類や様式がどれほど多様であったとしても、地球上のあらゆる地域に生息する人間に言語現象が顕現しているのは、そのような能力が人の身体に先天的に備わっているからだというのは直観的だろう。