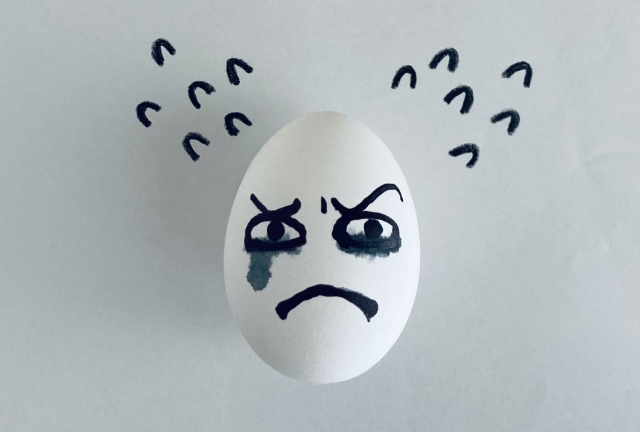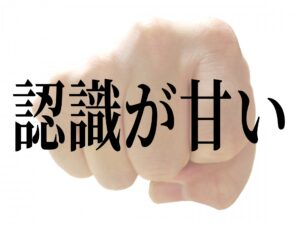テストで点数が悪かった。
―「しょうがない。」
この一言、あなたも口にしたことがあるのではないでしょうか。
けれど、この反応の中には、実はその人の「思考の癖」や「現実との向き合い方」が隠れています。
■1.「しょうがない」は、思考停止の合図
「しょうがない」と言えば、心は少し楽になります。
けれど同時に、「なぜ悪かったのか」を考えるスイッチが切れてしまう。
勉強において、いちばん危険なのは「反省できないこと」です。
「しょうがない」はその入り口になりやすい。
■2.「しょうがない」には2種類ある
同じ言葉でも、中身はまったく違います。
- 逃げのしょうがない
→「自分にはどうにもできない」と決めつけて、行動を止める。
例:「部活があったし、しょうがない」 - 受け止めのしょうがない
→現実を認めたうえで、次の行動に移す。
例:「今回はしょうがない。でも次はこう変える」
前者は“終わりのしょうがない”。
後者は“始まりのしょうがない”。
ほんの一言の違いが、未来を分けます。
■3.「しょうがない」と言う前に
本当にしょうがなかったのか?
時間の使い方、集中度、準備、優先順位。
どれかを変えれば、結果は変わったのではないか?
そう問い直すだけで、次のテストの準備が始まります。
「しょうがない」で終わる人は、そこで止まる。
「しょうがない」を起点にできる人は、そこから動き出す。
■4.さいごに
「しょうがない」と言うたびに、成長のチャンスを一つ失う。
けれど、現実を受け止めて、次を見据える「しょうがない」なら―
それは、次の挑戦への第一歩です。