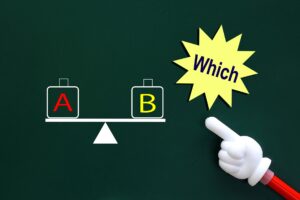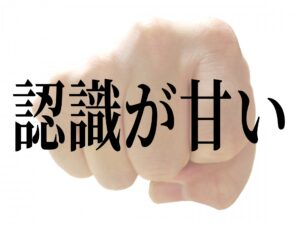授業中、「人の話を聞いていないな」と感じる瞬間がある。
しかもそれは、理解力の問題ではなく、姿勢の問題であることが多い。
たとえば英語の授業で、「『あなたは私の恩人です』の主語は何か?」と聞いたところ、ある生徒がこう答えた。
「you です」
いや、待て。
「あなたは私の恩人です」のどこに “you” がある?
そんな単語はどこにもないじゃないか!
この文の主語は、明らかに「あなたは」である。
日本語の主語を聞かれているにもかかわらず、英語に訳したうえで答えてしまう。
それは質問の意図をまるで理解していないということだ。
おそらくその生徒は、「英語の授業だから英語で答えるべき」と、勝手に判断したのだろう。
だが、そうした“思い込みによる先回り”が、かえって的外れな解答を生む。
これはまさに、「人の話を聞いていない」状態である。
自分が答えたいように答えただけなのだ。
実は何も頭を使ってない。
似たようなことは他にもある。
次の英文を見てみよう:
There are many good places to see in Japan.
この文で、「to see」の不定詞の用法を尋ねたところ、生徒は「副詞的用法」と答えた。
それは誤答である。
そこで、「じゃあこの不定詞はどこにかかっているのか?」と聞き直すと、
返ってきた答えは、
「あ、形容詞的用法でした!」
……そうではない。
聞いているのは「どの語句にかかっているか」であって、「用法の分類」ではない。
この場合、”to see” は “places” を修飾している。
正しい答えは「places」である。
それなのに、言われた質問の中身には耳を傾けず、
「正解と思われる言葉」だけを返して済ませようとする。
本質を理解せず、形だけを追っても力にはならない。
なぜそうなるのか。
理由は明確だ。
話を正確に聞こうとしていない。
「めんどくさい」「早く終わらせたい」「正解さえ出ればいい」
そんな気持ちが見え隠れする。
しかし、それでは勉強は身につかない。
その場をやり過ごすことはできても、思考力も応用力も育たない。
人の話には、順序と意図がある。
聞かれたことにきちんと耳を傾け、まず“何を求められているのか”を理解する。
それを怠って、自分の都合や思い込みで“それっぽい答え”を返していては、
本番のテストでも同じミスを繰り返すだけである。
これは、教科の内容に限った話ではない。
「メモを取りなさい」「図を写しなさい」と言われたら、サッと動く。
その一つひとつの反応が、やがて大きな差になる。
聞かれたことに対して動かない。ボーッとして流す。
そんな姿勢が積み重なれば、どれだけ内容を理解していても、結果にはつながらない。
だからこそ、声を大にして言いたい。
人の話を、ちゃんと聞け。
この“当たり前”ができていない限り、勉強しても、授業を受けても、成績は伸び悩む。
逆に、これがしっかりできる者は、吸収力も判断力も格段に高まる。
勉強の前に、まず姿勢を整えよ。
それが、どんな知識よりも強力な「土台」となるのだから。