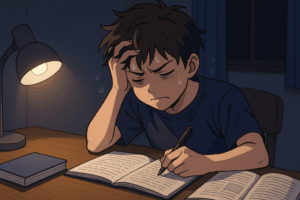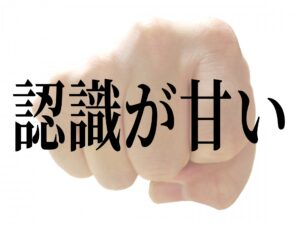「うちの子には○○があるから、無理なんです。」
こうして最初から限界を定め、可能性にフタをしてしまう家庭は少なくない。
集中力がない、体力がない、部活がある――いずれももっともらしく聞こえるが、その時点で成長の道は閉ざされる。
今できないのは当たり前だ。だからこそ、できるようにする場が必要なのであり、それが塾の役割である。
通ううちに集中力はつき、体力もつく。忙しい中でどう工夫して取り組むかを学ぶことこそが、成長に直結する。
実際に結果を出している家庭には、共通するものがある。
それは、親の覚悟である。
「やれるかどうか」ではなく、「やれるようにするにはどうするか」という視点で、日々の判断を下している。
子どもが「無理そう」「やりたくない」と言ったとしても、すぐに引き下がるのではなく、
「それでも今やるべきことかどうか」を大人の目線で見極め、必要であれば背中を押す。
一度始めたことに対しては、「続けさせる」「乗り越えさせる」という姿勢を持ち続けている。
もちろん、無理に押しつけているわけではない。
本人の意思は尊重しつつも、最終的な判断は親が責任を持って下している。
この“責任ある関わり方”こそが、子どもの土台を築き、やがて結果へとつながっていく。
一方で、「勉強しているのがかわいそう」「注意されてかわいそう」といった言葉を口にする保護者もいる。
確かに、目の前で疲れている子どもや、注意を受けてしょんぼりしている姿を見ると、何とかしてあげたくなる気持ちも理解できる。
だが、それにすぐ反応してブレーキをかけてしまっては、子どもは困難を乗り越える力を育てることができない。
必要な負荷を与えることをためらわず、目先の反応よりも先の成長を信じて関わること。
それこそが、教育的な関わり方である。
もちろん、子どもの気持ちに耳を傾けることは大切だ。
だが、「気持ちを聞く」ことと「判断を委ねる」ことは違う。
子どもはまだ、判断の基準や視野を持ち合わせていない。
だからこそ、大人が方向を示す責任がある。
「うちの子には無理」と言うか、
「うちの子を伸ばしたい」と言うか。
その一言が、子どもの未来を大きく左右する。
その選択をするのは、親である。