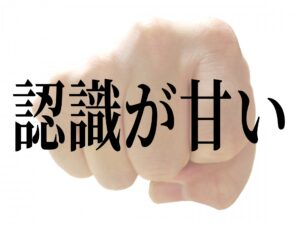■ 子どものひと言ににじみ出る「家庭の教育観」
教室で、こんなやりとりに出くわすことがある。
「あの…うちの親が、それはやらなくていいって言ってて…」
「先生、それはちゃんと話してくれって、親が言ってました」
「ぼくはいいけど、親が怒るので…」
本人の意思が見えない。
代わりに出てくるのは、「親が…」「母が…」という言葉ばかり。
これはつまり、“親の言葉を盾にしている”状態である。
■ モンペ的家庭の特徴:子どもを「代弁者」にしてしまう
このような発言が続く背景には、モンスターペアレント(モンペ)にありがちな特徴がある。
- 子どもに直接言わせることで、自分は関与せず、圧をかける
- 子どもを通して、「家庭の意向」を押し通そうとする
- 自分の考えが正しいという前提で、他者を変えようとする
この結果、子どもはどうなるか。
👉 「自分の言葉で話す」ことを学ばない。
👉 「誰かの意向に従って動く」ことが当たり前になる。
自分の頭で考え、責任をもって判断し、意見を伝える。
――その当たり前の成長が、家庭の“干渉”によって止められてしまう。
■ 一方、良質な教育ママの子は…
一方で、良質な教育ママの家庭では、子どもにこんな姿勢が見られる。
「自分で決めたことなので、やります」
「家で少し考えてみたけど、やっぱり必要だと思いました」
「前に先生に言われたこと、ちゃんとメモしてました」
「母も『自分で納得して動くことが大事だよ』って言ってました」
親の言葉が出てこないわけではない。
だがそこには、自分の意思と言葉がしっかりと通っている。
良質な教育ママは、「親の代弁」ではなく「子ども自身の判断」を尊重している。
だからこそ、子どもは自分で考え、自分で動くことを当たり前にしている。
■ 子どもの“口調”は、家庭の写し鏡
大人が子どもにどんなメッセージを送り、どんな姿勢で接しているか。
それは、言葉ではなくても――いや、むしろ子どもの“ひと言”に確実に現れる。
「親が言っているので…」という口癖の裏には、
親の過干渉、あるいは過信の構造が見え隠れする。
■ 子どもは、自分で伸びようとする力を持っている
我々大人が思う以上に、子どもは強い。
自分の言葉を持ち、自分の責任で動こうとする力を、もともと内に秘めている。
大人の役目は、それを「代わってやる」ことではなく、
「引き出してやる」こと。
信じて、任せて、見守る―
その姿勢こそが、将来、社会の中で自分の足で立てる人間を育てていくはずだ。