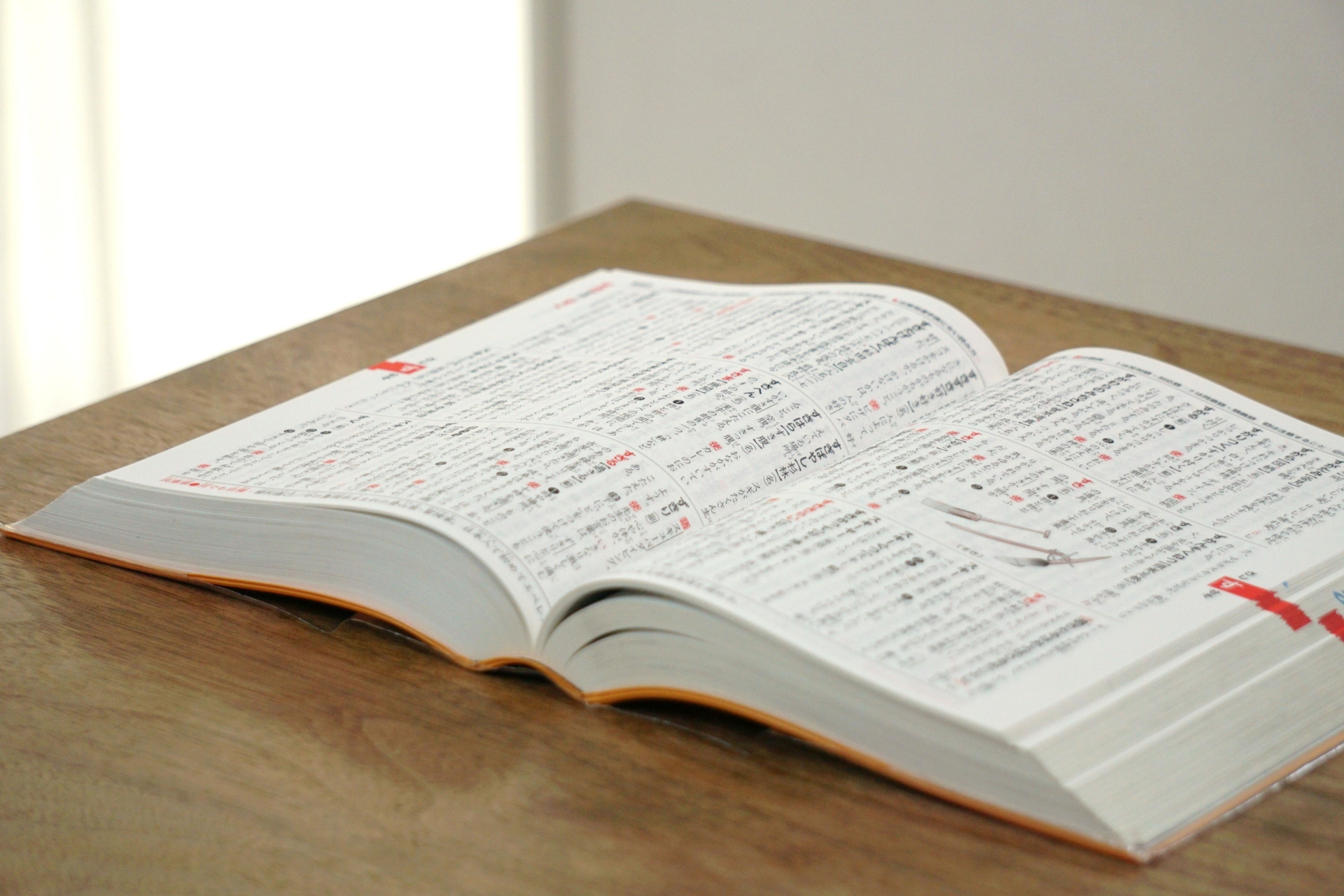国語の文章問題には、
「( )に入る適切な接続語を選べ」
という問題があります。
そのときに迷いやすいのが、
「では」 と 「さて」 です。
どちらも「話の流れを変える」ときに使われますが、
文章の中では役割がまったく違います。
◆「では」=前の内容を踏まえて“次の段階へ進む”言葉
「では」は、前に書かれたことを受けて、
次の説明・疑問・結論につなげるための言葉です。
- 「A とわかった。 では、B はどうか考えよう。」
- 「A だと言える。 では、なぜそうなのか?」
ポイントは、
前の内容を踏まえて、一歩深く話を進める。
ここが文章読解で大事になる。
◆「さて」=話題転換・段落替えの言葉
「さて」は、
前の話から少し距離を置いて、話題を切り替えるときに使います。
- 「ここまでが前置き。 さて、本題に入ろう。」
- 「さて、次は別の視点から考えてみよう。」
特徴は、
前の内容を受けて“深める”のではなく、方向を変える。
◆例で比べると一目瞭然!
●例文
公共性は法律と同じ約束事である。
( )、なぜ多くの科学者は客観を約束事だと思わないのか。
ここで入るのは 「では」。
理由:
前の情報(公共性=約束事)を踏まえて、
次の疑問に進んでいるから。
「さて」だと単なる話題転換になってしまい、
文章の論理として弱くなる。
◆まとめ
| 接続語 | 役割 | イメージ |
|---|---|---|
| では | 前を踏まえて、次の段階へ進む | 「よし、次の話に“発展”するぞ」 |
| さて | 話題・段落を切り替える | 「気分を変えて“別の方向”へ」 |
とくに国語の空欄補充では、
前の内容 → 次の疑問・説明 、一歩深める→「では」
前の内容 → 話題を変える →「さて」
こう考えるとミスがぐっと減ります。
🔷練習問題 ではorさて 1つだけどちらも入らないものがあるが、それは?
(1)
気温の上昇が続いている。( )、原因について詳しく見ていこう。
(2)
ここまでが調査結果の説明だ。( )、次はその意味を考えてみよう。
(3)
この作品は作者の幼少期の経験をもとにしている。( )、内容を読み取るうえで何が重要だろうか。
(4)
これまでの議論は基礎的な部分だった。( )、ここから応用的な視点に移る。
(5)
私たちの生活は便利になった。( )、その裏で失われつつあるものもある。
(6)
この章では光合成の仕組みを確認した。( )、次章では実験データを見ていく。
(7)
A校とB校の生徒数を比べると、大きな差がある。( )、その理由はどこにあるのだろうか。
(8)
ここまで具体例を示してきた。( )、全体としてどんなことが言えるだろうか。
(9)
まず前提となる考え方を整理した。( )、本題となる議論に入る。
(10)
この問題は単純なミスが原因だ。( )、どんな対策が必要なのか考えてみよう。
◆【解答】
(1)では
(2)さて
(3)では
(4)さて
(5)どちらも不可(「しかし」「一方で」が適切)
(6)さて
(7)では
(8)では
(9)さて
(10)では